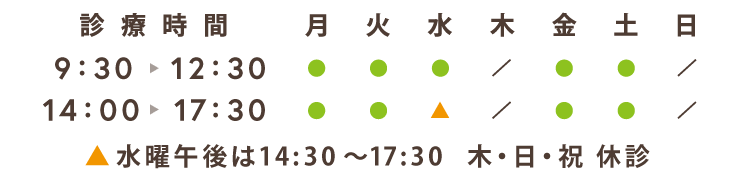こんにちは。名古屋市天白区にある歯医者「医療法人IDGいちろう歯科・矯正歯科」です。
普段何気なくしている“噛む”という行為について考えたことはありますか?
「子供によく噛んでね、って伝えているけど理由が分からない」という人も多いかと思います。
この記事では“噛む”ことの目的や重要性について解説します。

目次
「噛む力」が注目されている理由
“よく噛んで食べなさい”は、なぜ大切なのか?
親や学校の先生に「よく噛んで食べなさい」と言われて育った方も多いと思います。
この言葉には、単に“食事マナー”という意味だけでなく、成長期の子どもの身体や脳の発達を支える大切な意味が込められています。現代の食生活では、柔らかいパンや加工食品、スムージーなど、“噛まなくても食べられるもの”が増えています。
その結果、噛む回数は昭和時代と比べて半分以下になったとも言われています。
実は「噛む」という行為には、以下のような多くの働きがあります:
顎の骨の成長を促す
顎骨が成長するので歯並びが整いやすくなる
唾液分泌を促進し、むし歯・感染症を防ぐ
脳への刺激で集中力が上がる
つまり、“噛むこと”は、歯だけでなく全身の発育や学習能力にまで関わる重要な動作なのです。
現代の子どもたちが“噛まなくなっている”理由とは?

昨今、子ども達が噛まなくなっていると言われています。
なぜ今の子どもたちは噛まなくなっているのでしょうか?
そこには以下のような要因があります:
加工食品や柔らかいパン、麺類など“噛まずに飲み込める”食品が増えた
忙しい食事時間や“ながら食べ”により、ゆっくり咀嚼する習慣が失われている
顎を使う遊び(硬いものを噛む、よくしゃべる、外で活発に動く)が減っている
スマホや動画の影響で、姿勢が悪くなり噛みにくくなっている
このような生活環境の変化が、子どもたちの噛む力を弱くし、歯並びや顎の発育に影響を与えているのです。
「噛む力」は、意識して育てなければどんどん失われていきます。
【噛む力と歯並び】顎の発達と歯列の関係を考える
噛む回数が減ると、顎はどうなるのか?
噛む回数が減ることで、顎の筋肉や骨に十分な刺激が加わらず、顎が小さく・細く成長してしまう傾向があります。
顎の骨は「刺激によって成長する」ため、よく噛むことで骨がしっかりと広がり、歯が並ぶスペースが確保されやすくなります。
しかし現代の食事は、柔らかいもの中心。子どもたちは食事の際、昔よりも明らかに噛む回数が少なくなっており、これが顎の未発達につながっています。
顎が十分に育たないと、永久歯がきれいに並ぶスペースがなくなり、歯並びの乱れの原因となってしまいます。
歯並びの乱れは、見た目だけの問題じゃない
歯並びの悪さは「見た目の問題」として捉えられがちですが、実はそれだけではありません。
噛み合わせのズレにより、片側だけで噛む癖がつくと、顔や体のバランスにも悪影響が出る可能性があります。
さらに、歯が重なっていると汚れがたまりやすく、むし歯や歯周病リスクも上昇。発音や咀嚼機能、さらには呼吸(口呼吸)にも影響が出るケースもあります。
つまり歯並びは、「健康的な口腔環境」を保つための大切な基盤なのです。
噛む力と歯並び、矯正だけで解決できる?
矯正治療で歯並びを整えることはもちろん有効ですが、根本的な原因である「噛む力の低下」や「顎の未発達」が改善されない限り、後戻りや別の問題を引き起こす可能性もあります。
当院では、矯正装置による治療に加え、「噛む習慣を育てる指導(アクティビティ)」など、生活習慣の改善にも注力しています。
噛む力を意識的に育てていくことが、将来のトラブルを未然に防ぎ、安定した歯並びの維持につながります。
【噛むことで脳も育つ?】学力・集中力との関係
噛むことが“脳”を刺激するって本当?
噛む行為は単なる消化の補助ではなく、脳への血流を増やす“刺激”の一種です。
特に「前頭前野(集中力や思考力を担う領域)」が活性化されることがわかっており、子どもの発達においては非常に重要です。
朝食でしっかり噛んで食べた子どもは、午前中の授業での集中力が高まるという研究もあります。
噛むことで脳が“目覚める”とも言える状態が作られ、学習効率にも影響しているのです。
噛む力が落ちると、姿勢や集中力にも悪影響?
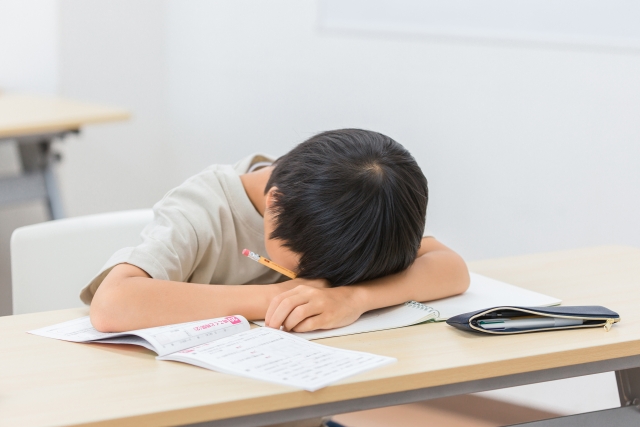
噛む力が弱い子どもは、顎が安定しないために姿勢が崩れやすくなり、座っているだけで疲れやすくなる傾向があります。
そうした身体的な不安定さは、結果的に集中力の低下や注意力の散漫さにもつながります。
当院でも、学童期の矯正相談で「集中力が続かない」「口がポカンと開いている」などのご相談を受けることがあります。
実はその背景に、「噛む力の弱さ」や「顎の成長不足」が隠れているケースも少なくありません。
【家庭でできる!噛む習慣の育て方】
日常の食事に“噛むトレーニング”を取り入れてみましょう。
特別な道具やプログラムは必要ありません。毎日の食事で「噛む食材」を意識的に選ぶだけでも大きな変化が生まれます。
例えば:
一口大に切っていたのをやめ、歯でかじるように大きめに切る
ごぼう、れんこん、きのこなどの歯ごたえある野菜を食べる
おにぎりを硬めに握る
するめや小魚をおやつに取り入れる
また、よく噛むことで味を感じやすくなり、食事の満足感も高まります。食育の観点でも非常に効果的です。
「姿勢・食べ方・環境も“噛む力”に影響する」
噛む力を育てるには「食材」だけでなく、「食べる環境」や「姿勢」も大切です。
例えば:
足がしっかり床につく高さの椅子を使う
テレビやスマホを見ながらの“ながら食べ”を避ける
1口30回を目安に噛むよう声かけする
こうした日常の工夫が、自然と噛む回数や質を高め、歯並びや顎の成長にもよい影響を与えます。
【歯科医院と一緒に】矯正治療+生活習慣の改善
装置だけに頼らない、“噛む力”を育てる治療
一般的に矯正治療というと、「装置で歯を動かすこと」が注目されがちですが、
本当の意味でのきれいな歯並びのためには、口腔周囲の筋肉機能の正常化が欠かせません。
当院では、小児の矯正治療においても、「噛む・飲み込む・話す・呼吸する」などの口の使い方=MFT(口腔筋機能療法)をアクティビティとして楽しく取り入れています。
舌や唇、頬の筋肉のバランスを整えることで、装置による矯正がスムーズに進み、後戻りのリスクも減らすことができます。
「噛む」「飲み込む」「正しく口を閉じる」という基本的な力は、装置だけでは身につかない部分です。
だからこそ、お子さんの成長に合わせた“育てる矯正”が大切なのです。
マイオブレスを活用した“姿勢と呼吸”からのアプローチ

当院では、成長期のお子さまに対し「マイオブレス」や「プレオルソ」というマウスピース型装置を用いた矯正治療も行っています。
これは歯を直接動かすものではなく、口呼吸・舌の位置・姿勢・筋肉の使い方など“原因”にアプローチする治療法です。
これらの装置は、正しい口の機能を習慣化するトレーニングとセットで使うことで、
歯並びを悪くしていた根本的な癖を改善する効果があります。
姿勢が良くなり、口が自然に閉じられるようになると、噛む力や集中力にもよい影響を与えるケースも多く見られます。
“歯を並べる”のではなく、“なぜ歯が並ばないのか”を考えるのが、当院の矯正治療の考え方です。
装置・トレーニング・生活習慣の三本柱で、お子さまの成長をサポートします。
まとめ

噛むことは顎骨の発育や歯並びだけでなく脳の発達や集中力にも関与しているため非常に重要な事です。
日々の何気ない癖が将来の歯科的な問題につながることもあるからこそ、
早い段階で気づき、適切なサポートが大事になってきます。
いちろう歯科・矯正歯科ではMFT(口腔筋機能療法)を楽しく行うアクテビティとして取り入れながら、
子供たちが前向きに取り組めるように工夫しています。
またマイオブレスやプレオルソなど最適な装置を用いて口腔機能の改善とともに健やかな成長を支えていきます。
お子さまのお口周りの癖が気になる方、矯正治療をした方が良いか悩んでいる方はお気軽に当院へご相談ください。