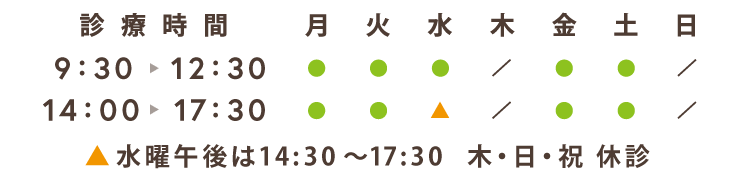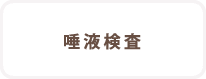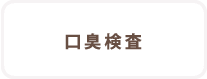- ホーム
- 診療案内:歯科ドック
- 歯科ドック
-
名古屋市天白区の歯医者 いちろう歯科・矯正歯科では、歯科ドックをはじめとして
いろいろな検査を実施し、患者さんの「健口」をサポートしています。
ご自身の抱えるリスクを把握していただき、効果的な予防にお役立てください。
歯科ドック
(リスク管理検査)とは
- 歯科ドックの重要性
-
当医院では、新しい概念として「健口歯科」を提唱しています。
これを実現するためになくてはならないのが、リスク管理検査です。予防の重要性を理解していただくには、患者さんご自身が、ご自身の体について気付きや関心を持っていただく必要があると考えています。またご自身が抱えるリスクを知っていただいた上で、それぞれに適した提案やアドバイスを聞いていただければ、予防歯科に対して前向きに取り組むことができると考え、当院では歯科ドックを推奨しています。歯科ドックでは、細菌培養検査、口臭検査、唾液緩衝能検査、唾液量検査等いくつかの検査を行い、総合的にリスクを出していきます。これにより1年後の虫歯にかかる確率やその回避の方法、その他その人に合った最適な予防方法などが見えてきます。

- ご自身の虫歯リスクを知るために
すべての患者さんに歯科ドックをおすすめします -
当院では、そもそも検査無きものは医療ではないと考えています。また、当院の医療の流れの大原則として「原因の除去⇒機能の回復⇒再発の予防」があります。
今までの歯科治療は、この中の「機能の回復」だけを一生懸命やってきました。しかし、これは一時的な効果しかありません。前後の「原因の除去、再発の予防」こそ、医療本来の目的ではないでしょうか。
ここをしっかり行っていくためには、リスク検査が必要不可欠となります。
今まで虫歯や歯周病になった経験のある人はもちろん、一度もなったことがない人でもリスクはあります。例えば細菌が多いにもかかわらず唾液の力が強く、カバーされていただけかもしれません。ストレスやお薬、食生活の変化などで、唾液の力が弱まると、一気に臨界点を超え、虫歯が多発する場合もあります。
またそういったお母さんが、お子さんに菌を感染させてしまうこともあります。「自分は虫歯がないのに子供は虫歯だらけなのです。」なんてことを言われる方に、実は自分が感染源だったこともあります。いずれにせよ、全ての方にリスク管理検査である「歯科ドック」はおすすめします。

中学生以上になると、これまでの生活習慣の中で、お口の環境はほぼできあがっている状態になります。とはいえ、この時期からでもお口の環境を改善することは可能です。
改善のためには、これまでの生活習慣の中でできあがっている環境を、科学的に数値として把握することが重要になります。歯科ドックでは虫歯の実体を把握してコントロールする学問をもとにしたリスク数値(カリオグラム)を測定し、個別に対処することでお口の環境を改善させていきます。
逆に言えば、お口の中の虫歯菌の数や、患者さん自身の唾液の力などをご自身で把握しなければ、歯を守ることは難しいのです。客観的数値をもって現状を把握することで、原因からその対処法までを明確にしていきましょう。これらによって、虫歯は100%予防できるものであるとされています。
- 虫歯リスクを抱えている患者さんへ
-
虫歯リスクは大なり小なりすべての人が抱えています。知らないだけです。まずはどういったリスクがあるのかを知ってください。そしてご自身が、その中のどのリスクが高いのかを知っていただきたいと思います。
その上で、リスクに対してどういった対応が有効なのかを知ってください。そこまでできたら、後はかかりつけの歯医者さん(特に担当の衛生士さんを持ってください)とともにプロケアとセルフケアのすみ分けをし、リスクに応じた対処法をプロがアドバイスすることで、効果的に予防へとつなげていきます。

唾液検査について

- 唾液だけでこんなにわかる?!
知りたかった「なんで?」が
「なるほど!」に変わる! - 「唾液検査」と聞きなれない検査ですが、実はこの唾液からお口の状態について多くのことが分かるのです。複雑な検査はしません。専用のガムのようなものを5分間噛み続け、たまった唾液を都度紙コップにためていただくだけの簡単な検査です。
ここからわかる事は3つ。
①虫歯菌の量 ②唾液量 ③緩衝能の強さ
これらの結果によって予防方法も異なるので、検査結果を踏まえて担当衛生士から説明・提案をさせていただきます。
- 虫歯菌量の検査
-
唾液から採取した検体を
院内で培養して
虫歯菌量を調べます虫歯菌量が多いとやはり虫歯になるリスクは上がります。
虫歯の原因となる菌は1種類だけではありません。
当院の唾液検査では「ミュータンス菌」「ラクトバチラス菌」の
2種類の菌を院内で培養して調べます。
どちらの菌がどのくらいの量いるのかを確認し、それに合わせたアドバイスを行います。検査の流れ
-

- 唾液の採取
- 舌の上と唾液の中からの、むし歯菌の量を検出します。

-

- 培養
- 院内にて菌の培養を行います。

-

- 結果説明
- 一週間後に結果を聞きに来ていただき、むし歯予防のご説明をさせていただきます。
唾液検査で調べられる
虫歯菌唾液検査で調べる「ミュータンス菌」と「ラクトバチラス菌」は
それぞれ虫歯菌の一種ですが、作用する働きが違います。-
- ミュータンス菌
- 「ミュータンス菌」は、いわゆる虫歯菌です。
歯に残っている食べかすなどにくっつき、歯垢と呼ばれるプラークを形成します。
その中で繁殖し酸を出して、歯を溶かしていきます。
-
- ラクトバチラス菌
- 「ラクトバチラス菌」は実は虫歯菌ではありません。食物に含まれる善玉菌です。しかし、お口の中に限っては歯自体にくっつく事が出来ないので虫歯菌にくっつき、より虫歯を大きくしていく作用のある菌となります。
ミュータンス菌で虫歯が作られ、
ラクトバチラス菌で虫歯がより拡大していくのです。
どちらの菌も少ない方が、虫歯のリスクを低くできるということです。 -
- 唾液量の検査
-
唾液量は「多い」が良い
唾液の働きを
活性化させましょう唾液の量が多いと、お口の中の細菌や食べかすを洗い流してくれたり(自浄作用)、
虫歯菌や歯周病菌の増殖を抑える働き(抗菌作用)をしてくれます。
さらに、唾液中のカルシウムやリンの成分が歯を修復する「再石灰化」という働きによって、初期の虫歯は自然に修復されることもあります。
逆に唾液量が少ないと、上記のような作用が効果的に働きませんので、
虫歯や歯周病のリスクが上がります。
細菌数も増え、口臭の原因にもなります。検査の流れ
-

- ガムを5分噛む
- ガムを5分間噛んでいただき、唾液の分泌を促します。

-

- 唾液を紙コップに
ためる - 口内にたまった唾液を、都度紙コップにためていきます。
- 唾液を紙コップに

-

- 分泌量を計測
- 1分間のうちにたまった唾液量(ml/分)を計測し、唾液の分泌量を調べます。
唾液量を増やすには?
唾液量の少なさが与える影響は、お口の中では収まらず身体にも表れます。
そのため、唾液量を多くすることはご自身の健康を守るためにも
重要なことだといえます。等、日常的にできることから生活習慣の見直しまでさまざまありますので、
検査と生活習慣に関する問診の結果に合わせて、
歯科衛生士よりアドバイスさせていただきます。 -
- 緩衝能の検査
-
あまり知られてないけど
実は大切な機能
お口の中のバランサー本来お口の中は中性~ややアルカリ性に保たれていますが、食事や細菌の作用により酸性に傾きます。
緩衝能(かんしょうのう)とは、その酸性に傾いたお口の中を中性に戻す働きのことです。
お口の中が酸性になると、歯からミネラルが溶け出す脱灰(だっかい)が起こり、その時間が長ければ長いほど初期虫歯に進行してしまいます。
しかし、緩衝能の力で中性に戻していくことで、再石灰化を助け、唾液中のカルシウムやリンが歯に取り込まれる働きを促します。
緩衝能は、虫歯になりにくい環境を維持してくれる大切な機能なのです。検査の流れ
-

採取した唾液を
試験管に垂らす 
-

試験紙の色の
変化を見る
お口の中が酸性・中性・
アルカリ性になると
どんなことが
起きやすい?酸性
- 虫歯や酸蝕歯になりやすい
- 細菌が関与せず、飲食物に含まれる酸などにより歯のエナメル質や象牙質が溶けてしまう状態のこと。進行すると歯が黄色く見えたり知覚過敏の症状が出たりする。
中性
正常な状態
アルカリ性
- ややアルカリ性は正常の範囲
-
- 歯石が付きやすくなる
- 細菌バランスが乱れて口臭の原因に
緩衝能の力が弱くなる原因も唾液の量や質に由来するため、
唾液量を増やしていくことは重要◎
検査してみないと、緩衝能の強さは日常生活ではわかりません。
虫歯になりやすくて悩んでいる方は、ぜひ調べてみることをオススメします。 -
口臭検査について

- 自分の口臭を気にしたことはありますか?
もしかしたら口臭に気づいていないだけかも… -
外国人の7割が日本人の口臭にがっかりしており、その日本人の9割が無自覚だそうです。他人の口臭には気づいても自分の口臭には気づかないものです。口臭があっても他人はなかなか指摘しづらいので、気づかないまま過ごしている方も多いのではないでしょうか。
また口臭対策はその原因によって変わります。自己判断で必要以上に悩んだり、間違った対策をとってしまうことのないよう「口臭があるのか?あればその原因は何か?」ということを、科学的分析によってはじき出していきます。
口臭検査の流れ
-

- 口腔ガスの採取
- シリンジをお口の中に入れ、歯と唇でしっかりと固定し、1分間鼻で息をしてお口の中にガスを貯めます。プランジャーを引っ張って採取完了です。

-

- 測定
- 機械の中に採取したガスを注入して口腔内ガスを測定します。4分で測定が完了し、3種類の口腔内ガスが数値化されて出力されます。

-

- 結果説明
- 検査結果に基づき、口臭の有無や口臭原因の説明、今後の口臭対策について分かりやすくご説明いたします。
- 検査を終えた後のフォローについて
-
検査結果を元にフィードバック用紙を使って、頂いたお時間で歯科衛生士が個別に説明とアドバイスを行っていきます。また、結果からその人に合ったケア用品の処方箋もお出しします。
その後、メンテナンスで通っていただく際には、検査結果を参考に使用する用品を変えたり、処置内容を変えたりしています。また、1〜2年に一度、定期的に検査を再度受けていただく事で、経時的にリスクの増減、移り変わりなども把握でき、お役に立てると考えています。


- ご自身で気をつけてもらいたいこと
-
その人自身の持つリスクを明らかにすることがまず必要です。
虫歯になる原因は一つではなく実はいくつもあります。歯磨きの仕方なのか、食生活なのか、唾液の性状なのか、唾液の量なのか、口腔内細菌叢なのかなど。すべてを闇雲に注意するといっても、現実的には非効率です。人それぞれリスクの存在部位は異なります。まずはご自身にはどこにリスクが高くあるのか、何に気を付けるべきなのかを知ることです。
それを知るための検査を行っている歯医者さんへ行って、しっかり把握することから始めてください。
検査費用
|
7,000円 |
|---|---|
|
1,000円 |