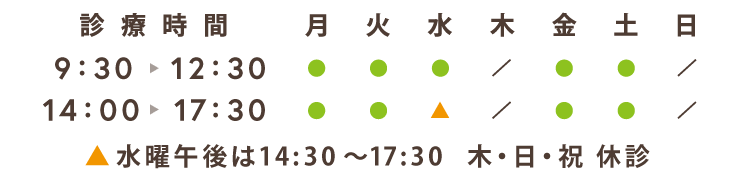こんにちは。名古屋市天白区にある歯医者「医療法人IDG いちろう歯科・矯正歯科」です。

歯医者で歯周病を指摘された方や、歯周病が疑われる症状が見られると「毎日歯磨きをしているのになぜ?」と疑問を抱くかもしれません。歯周病は、プラークと呼ばれる細菌の塊が蓄積することによって引き起こされる病気です。
しかし、プラーク以外にも、生活習慣や日々のストレス、持病などさまざまな要因が関連して発症するといわれています。そのため、毎日ブラッシングをしていても発症することがあるのです。
本記事では、歯周病になる原因や歯周病になりやすい人の特徴、予防するためのポイントなどについて解説します。
目次
歯周病になる原因

歯周病の直接的な原因は、プラークと呼ばれる細菌の塊です。不十分なブラッシングによって、歯と歯茎の間にあるすき間(歯周ポケット)にプラークが蓄積することで引き起こされます。
ただし、口の中に細菌が蓄積しているだけで炎症が起こるわけではありません。プラークの蓄積以外にも、患者さまのハグキの状態や免疫力、喫煙習慣、歯並び、食いしばりや歯ぎしりなどの癖、基礎疾患などが複雑に関連して進行するといわれています。
どのような人が歯周病になりやすい?

では、どのような人が歯周病になりやすいのでしょうか。ここからは、歯周病になりやすい人の特徴について解説します。
丁寧なセルフケアができていない人
歯周病の直接的な原因は、プラークです。そのため、丁寧なブラッシングができていない人やブラッシングをしない人は、当然ながら歯周病のリスクが高まります。
「忙しくてゆっくりメンテナンスをする時間がない」「夕食の後、歯を磨かずに寝落ちすることが多い」という方もいらっしゃるかもしれません。そのような生活を続けていると、歯周病が発症しやすくなるだけでなく、ハグキの炎症が悪化しやすくなります。
歯並びが悪い人
歯並びが悪い人は、そうでない人に比べて歯周病にかかりやすくなります。歯と歯が重なり合うように生えていたり凸凹していたりする場合、細かい部分まで歯ブラシが行き届きにくく、磨き残しが多くなるためです。
また、悪い歯並びによって部分的に大きな負荷がかかると、ハグキが下がり、歯周病のリスクが高まります。
糖分の多い食べ物を良く食べる人
歯周病や虫歯の原因となる細菌は、糖分をエサとして繁殖します。そのため、甘いお菓子やジューズなどを頻繁に口にする方は、歯周病にかかりやすくなります。また、柔らかい食べ物を好む人も歯周病のリスクが高くなるでしょう。
通常、私たちの口の中は、唾液で潤うことにより細菌が繁殖しにくい状態に保たれています。柔らかい食べ物ばかり食べていると、噛む回数が減って唾液の分泌量が低下し、歯周病を発症しやすくなります。
喫煙習慣がある人
喫煙習慣がある方は、そうでない方に比べて歯周病を発症しやすく、症状が悪化しやすいといわれています。タバコに含まれるニコチンや一酸化炭素などは、ハグキへの血流を阻害したり免疫力を低下させたりする原因となるためです。
また、喫煙によって唾液の分泌が抑えられることにより、細菌が繁殖しやすくなります。なお、喫煙習慣があると、ハグキの炎症が悪化しやすいだけでなく、治療の効果も出にくくなるといわれています。
口呼吸の人
先にも述べた通り、私たちの口の中は唾液の作用によって、細菌が繁殖しにくい状態に保たれています。普段から口呼吸をしている人や口をポカンと開けることが多い人は、口の中が乾燥しやすくなるため歯周病にかかりやすくなります。
歯ぎしりや食いしばりの癖がある人
歯ぎしりや食いしばりでは、歯や顎に非常に大きな力がかかるといわれています。歯や顎に過剰な負荷がかかり続けると、ハグキが下がったり顎の骨が吸収されやすくなったりするのです。その結果、歯周病が悪化しやすくなります。
持病などがある人
糖尿病の人や高血圧で降圧剤を服用している人など、持病がある人も歯周病にかかりやすくなります。
糖尿病の人は病気の影響によって免疫力が低下しやすいため、歯周病を発症しやすいといわれています。また、高血糖状態になると唾液の分泌量が低下することから、症状が悪化しやすくなるという特徴もあります。
一方、高血圧で降圧剤を服用している人や持病によって抗てんかん剤や免疫抑制剤などを服用している人も、薬の作用によって歯周病を発症しやすくなるため注意が必要です。
ストレスや疲労が溜まっている人
歯周病は炎症性の疾患ですので、免疫力が低下すると発症しやすくなります。日頃からストレスや疲労が溜まっている人は、免疫力が低下するだけでなく、緊張状態になることで唾液の分泌量が低下するといわれています。
また、慢性的なストレスは、歯ぎしりや食いしばりを誘発する原因にもなりますので、結果的に歯周病を悪化させる可能性が高くなります。
歯周病になるのを予防するには

歯周病を予防するためには、口腔内を清潔に保つことや生活習慣を改善することが大切です。ここでは、歯周病を防ぐための5つのポイントをご紹介します。
丁寧にブラッシングを行う
歯周病を予防するためには磨き残しをできるだけなくし、口腔内を清潔に保つことが重要です。特に、歯と歯のすき間や歯周ポケットにはプラークが蓄積しやすいため、細かく丁寧に磨くことを心がけましょう。
また、歯ブラシが行き届きにくい箇所には、デンタルフロスや歯間ブラシ、タフトブラシなどを使ったセルフケアを徹底しましょう。「汚れがしっかり落とせているか不安」「フロスの有効な使い方を知りたい」という方は、お気軽にクリニックへご相談ください。
悪い癖を改善する
健康なハグキを維持するためには、口呼吸や歯ぎしり、食いしばりなどの悪い習慣を改善することも大切です。口呼吸には鼻の病気や歯並びなどが関係していることもありますので、まずは原因を明らかにして対処する必要があります。
また、歯ぎしりや食いしばりは無意識に行っていることが多いため、必要に応じてマウスガードを作製することも、歯周病予防につながるでしょう。
禁煙する
喫煙習慣があると歯周病を発症しやすくなるだけでなく、炎症が悪化しやすくなります。また、治療の効果も得られにくくなりますので、できる限り禁煙することが望ましいでしょう。
自分でタバコを減らすのが難しいという方は、一度クリニックへご相談ください。
生活習慣を改善する
歯周病を予防するためには、生活習慣を改善することも大切です。普段から甘い物をよく口にする人は、甘い物を控えるようにしたり飲食した後はこまめにブラッシングしたりするとよいでしょう。
また、ストレスや疲労を抱えている人は、睡眠時間を確保したりストレスを発散したりすることを意識してみてください。バランスの良い食事や適度な運動、質のよい睡眠を心がけ、免疫力を下げないようにすることが歯周病の予防につながります。
定期的にクリニックを受診する
毎日しっかりとセルフケアをしていても、磨き残しは生じるものです。そのため、定期的にクリニックでクリーニングを受けることも重要です。
クリニックでは、プロの専門的なクリーニングによって、普段のブラッシングでは落としきれない汚れを徹底的に除去できます。患者さま一人ひとりに合ったブラッシング指導や生活指導も受けられますので、ぜひお口の健康にお役立てください。
なお、定期的なメンテナンスは3~6ヵ月に1回程度を目安に受けるとよいでしょう。
まとめ

歯周病は磨き残しによるプラークの蓄積だけでなく、患者さまの生活習慣や健康状態によって引き起こされることもあります。丁寧にセルフケアができていない人や喫煙習慣がある人、食いしばりなどの癖がある人、ストレスや疲労を抱えている人などは特に注意しましょう。
なお、お口のトラブルを防ぐためには、定期的にメンテナンスを受けることも重要です。「ブラッシングのときに血が出るようになった」「口臭がきつくなった気がする」など、気になる点があればお気軽に歯科医院へご相談ください。
歯周病を予防したいと考えている方は、名古屋市天白区にある歯医者「医療法人IDG いちろう歯科・矯正歯科」にお気軽にご相談ください。
当院は、健康なお口=健口から健康を創り出す歯科医院として予防を中心とした歯科医療を提供しています。予防歯科や小児矯正、マウスピース矯正だけでなく、虫歯・歯周病治療やホワイトニング、入れ歯、歯科ドックなども行っています。